「うちの子、将来のために早くから何かさせた方がいいのかな?」
そう考えて、幼児教室や早期教育を検討している方もいるかもしれません。
実際、私の周りでも「〇〇ちゃんはもう英語ペラペラらしいよ」「△△くんは小学校の内容まで終わってるって」なんて話を聞くと、焦りを感じてしまうこと、ありますよね。
でも、ちょっと待ってください!
個別指導塾のTOMAS(トーマス)が運営する中学受験情報メディア[スカラ]に、教育評論家の親野智可等さんが書かれた興味深い記事がありました。それは、**「子育てや教育における迷信が、学問的研究によって打ち破られる」**という内容。(出典:子育てや教育における迷信が、学問的研究によって打ち破られる~親野智可等)
この記事を読むと、これまで私たちが「正しい」と信じてきた子育ての常識が、実はそうではないかもしれないという驚きの事実が明らかになっているのです。
え?小さい頃に遊んでいた子の方が賢いってホント?
特に私が注目したのは、「小さいときから勉強させたほうが、いい大学に行ける?」という疑問に対する研究結果です。
なんと、お茶の水女子大学名誉教授の内田伸子先生の研究によると、偏差値68以上の難関大学に合格した子どもたちは、そうでない子どもたちに比べて、小学校入学前にたっぷり遊んだり、自分の好きなことに夢中になったりしていた割合が圧倒的に高かったというのです!
さらに、幼児期に本人の主体的な遊びを重視し、「非認知能力」(意欲、集中力、自制心、やり抜く力など、学力以外の生きる上で重要な力)を育むような教育を受けた子どもは、その後の人生においても、勉強や仕事に意欲的に取り組み、結果として学力や収入が高くなる傾向があることも分かっています。
早期の「お勉強」がもたらす意外な落とし穴
この話を聞くと、「早くから塾に通わせて、先取り学習をさせてきたのに…」と複雑な気持ちになる親御さんもいるかもしれません。
確かに、幼児期から熱心に読み書きや計算などの「お勉強」をさせてきたという話はよく聞きます。中には、小学校低学年で高学年の内容まで進んでいるケースもあるようです。
しかし、私の経験から言えるのは、幼少期の過度な先取り学習が、必ずしもその後の学力向上に繋がるとは限らないということです。
子どもたちは、新しいことや興味のあることには目を輝かせ、驚くほどの集中力を見せます。
しかし、早期に詰め込んだ知識は、表面的で本質的な理解を伴っていないことが多く、「なんとなく知っている」という状態になりがちです。
そのため、本当に理解が必要になった段階で伸び悩んでしまったり、知っているつもりになっているために真剣に取り組まなくなってしまうことがあるのです。
ぐんぐん伸びる子の親がしていた「あること」
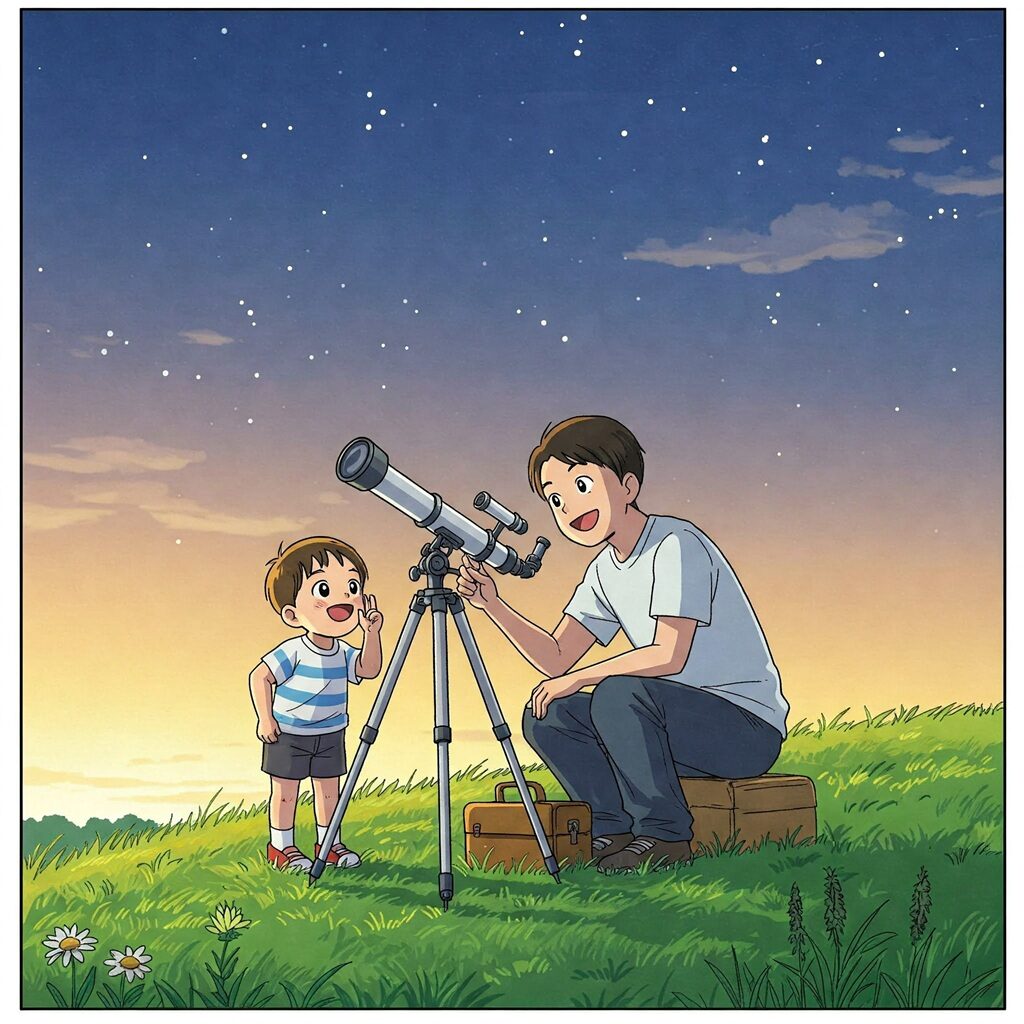
一方、小学校高学年から目覚ましい成長を見せる子どもたちの親御さんに話を聞くと、幼い頃から勉強以外の好きなことに熱中させてきたという共通点が多くあります。
- 電車が好きなら、家族で鉄道旅行に出かけたり、図鑑を一緒に読んだり。
- 絵を描くのが好きなら、自由に絵の具や画材を与え、美術館に連れて行ったり。
- 外で遊ぶのが好きなら、時間を気にせず思いっきり遊ばせたり。
親が手を貸すのは、子どもが夢中になれる何かを見つけるきっかけを与え、見つかったらその興味を深く追求できるようサポートすること。
もちろん、小学校低学年までの学習内容をきちんと身につけることは大切ですが、それ以上に、子どもが自ら興味を持ち、主体的に取り組む姿勢を育むことの方が、将来的な学力向上にはるかに重要なのです。
小学校3年生までの親がすべき「たった一つのこと」
では、小学校3年生までのお子さんを持つ親御さんは、具体的に何をすれば良いのでしょうか?
それは、お子さんの「好き」を大切にし、思いっきり遊ばせることです。
公園で泥だらけになって遊ぶ、虫を追いかける、絵を描く、積み木で想像の世界を作る、物語を読んで聞かせる…
これらの遊びを通して、子どもたちは好奇心、探求心、集中力、想像力、コミュニケーション能力といった、生きていく上で本当に大切な力を自然と身につけていきます。
焦る気持ちもあるかもしれませんが、どうかお子さんの「今」を大切にしてあげてください。土台がしっかりしていれば、その後は必ず力強く成長していき、ぐんぐん伸びていきます。
私たち親ができることは、早期教育に心を悩ませるよりも、お子さんが夢中になれる環境を与え、その興味を温かく見守り、応援することなのです。